
Paul Sezanne
1839-1906
写生に出かける
セザンヌ 1873
- 色彩にせまるモネの映像化
- セザンヌの光学理論批判
- 恐ろしい世間
- セザンヌの現象学的方法
- 時間を集積するタッチ
- タッチが生む運動性
- 事物の本質<充実>
- カメロンの写真とセザンヌの肖像画
- セザンヌの映像化からの離脱
色彩にせまるモネの映像化
モネの光学理論を取り込み色彩の強度を上げようとする試みは、テクノロジーの壁によって挫折しています。彼の色彩の瞬時にせまる映像化はの試みは、結局は瞬時の探求とはなり得ませんでした。しかし、画面におかれるタッチのひとつひとつは画家が対象から得る時間ごとの認識と画家が制作に要した現実の時間とシンクロするある構造的な対応がなされ、それが水蓮と画家のあいだを流れる時間のリアリティの表現となっています。
モネは色彩の瞬時を追求しながら、結果として持続する時間の表現に踏み込んでいました。モネのはじめた点描法(色彩のタッチによる描法)は、画家が視覚から認識にいたる時間をより構造的、分析的に絵画化しようとする試みとしてセザンヌに受け継がれていきます。
光学理論を批判するセザンヌ
モネの目に感嘆しつつその限界をみたたセザンヌは、「アンプレッショニスムとは何と言うのかね。ごった返った色覚さ。画布の上で色調をばらばらにする。網膜の上で、これを掻き集める。そんな事は、乗り超えて進まねばならない。」と印象派を批判します。
そして彼は「画家にとって光は存在しない」何故なら「光を生み出す訳にはいかないのだから、他のものを借りて、これを現さなければならない。この他のものとは即ち色だ。そうはっきり悟った時、私はやっと安心した。」と述べてモネの光学的な世界のとらえ方から離れます。
セザンヌにとっては、モネの対象をつつむ光の現象を追う営為も結局はテクノロジーの高度化という時代の動向に翻弄され自らの表現の根拠を見失うことのように映りました。また、絵画の映像化を進めたマネの絵も彼にはおそらく上質の風俗画以上のものではありませんでした。彼には、そのような方向は芸術を時代の流れに埋没させることに思えました。
恐ろしい世間から引きこもる
セザンヌは時代の先端をゆく都会に背を向け、自然と対峙するためにプロバンスの田舎に引きこもります。「再びクラッシックに還らねばならぬ。但し、自然によってである。というのは感覚によってである」と彼は語っています。
彼が選んだ時代の時空性に対峙する道は、テクノロジーの成果を追うことを止め、再び自然に向かい合う事でした。自然に向かい合い、再び個人の感覚によってのみ開示される世界を求めること、それが彼の言う「感覚の実現」でした。またそれが彼が取った近代の時空性のなかで、あやしくなった自己と世界の意味を問い直す方法でした。
彼の絵画を評価しはじめた世間の動向に対して「世間は恐ろしいものだ…」というセザンヌの言葉は、日常生活の厭わしさについての見解であると同時に、生身の人間を絡めとり振り回しにかかってくる時代の高度な時空性についての感慨でもあったのです。
テクノロジーの高度化は即人間自身の高度化を意味する訳ではない。そんな動きに惑わされずに自然と向かいあい人間自身のありかたを掘り下げなければ自分自身を見失ってしまう..。絵画の危機はセザンヌにとってはそのように理解されました。
セザンヌの現象学的な方法
「フッサールによれば、ユークリッド幾何学によって準備されガリレイの天才によって近代ヨーロッパの世界の範型となった自然の理念化ないし数学化によって、われわれの直接経験的な世界が蔽われてしまったのである。」 「現象学」 木田 元
木田氏によれば、フッサールはすべては合理性によって支配されているとする自然科学の世界観は、人を直接体験から遠ざける、生活世界に着せられた「理念の衣」だと考えました。
彼のひらいた現象学によれば、近代意識にとって根深い先入観である「理念の衣」を脱ぎ捨て、根源的な生活世界に立ち還り、逆に理念の生成を解明することがあらたな世界を開示する方法なのです。
この現象学的還元と呼ばれる態度をメルロ.ポンティは、「最初の哲学的行為は、客体的世界の手前にある生きられている世界(le monde vecu)に立ち戻ること」だと言っています。
ここからセザンヌの隠遁をみると、客体的世界の像としてあたかも人間の知覚に取って代わらんばかりの写真映像に背を向け、生きられる世界に立ち戻り、生の感覚が掴んだ像を絵画として実現しようとする、現象学的な態度だということができます。
セザンヌにとっては、マネの瞬時を追い求める姿も、モネの光の追及も「テクノロジーの衣」とでも言うべき科学主義が先導する時代の動向によって、「感覚」が本来あるべきところから遠く離された姿のようにみえたのです。
時間の集積セザンヌのタッチ

リンゴと瓶と椅子の背の
ある静物,1904-06頃
セザンヌの水彩画、例えば<リンゴと瓶と椅子の背のある静物>1904ー06頃をみると、連続して撮影したネガを重ね焼きした写真のように多くの瞬時の映像が重なっているようにみえます。その効果は、彼のタッチから生まれています。彼は対象の観察を即ひとつの形態にまとめようとするのでなく、対象を観察した時点時点で前後の形がずれていくのをそのままに生かし、いくつものタッチとして画面に並列的に描き入れています。
マネの絵画の映像化の営為は、あたかも一瞬時の映像であるかのようにそれぞれの対象像をある一瞬に向かわせ画像を成立させることでした。ここまでみてきた絵画の映像化は永遠という時間をめざしていた従来の絵画の要素を瞬時に向けて集約してみる試みだったといえます。
マネの描くある対象Aの画像は実際は制作の時間経過t(1~n)のなかの要素の集積 ΣA’t(1~n)としてなされますが、その実時間は画像からは消去され、あたかも写真の瞬時の映像と同じく A’tx であるかのように表現されています。
PM = A’tx ← ΣA’t(1~n)
一方セザンヌは画像から実時間の要素を消去せずそのまま残しA’t1、A’t2 ~ A’tnと重ねていくことに表現の活路を見いだしました。それがタッチによる不整合な形の集積となって表現されました。
PS = Σ A’t(1~n)
タッチが生む運動性を持続させたいセザンヌ
小林秀雄氏は「近代絵画」のなかで、対象の形が重複し多重に震えるようにみえるセザンヌのタッチについて次のように述べています。
「セザンヌの色彩感受の道は徹底したものであって、光も他の物象と同様に色と見たし、空間さえ色と感じているようである。彼は、面(プラン)という言葉を好んで使っているが、色は到る処で、色彩あるプランとして現れる。震えるのは光の波ではなく、彼の言葉を借りれば、自然が呈示している様々な「プランの魂」が震えるのである。空間のプランも、青味を帯びた魂で震えている。」
「近代絵画」小林秀雄氏
セザンヌのねらいは、それぞれの瞬間に知覚した対象の形態を集積し、小林氏が「震えている」と評するところの、タッチの細い色面の運動性を生み出し、セザンヌ自身が「プランの魂」と呼ぶ、対象を満たし対象たらしめている要素を表現することでした。
そこで彼はそれぞれのタッチをあくまで等価なものとして置き、あるタッチが決定的な意味をもつのを注意深くさけています。何故なら、それによって対象の形が固定してしまえば、画面に形態のヒエラルキーが発生し、画家の意図は形態の追及にとどまることになります。
そこに残されるのは従来の描写技術としては凡庸で硬直した風景画です。しばしば彼の画面にみられる塗り残しは、もしそこにタッチを置けば画面上の運動が停止してしまうために塗らずに残されたのです。彼はタッチの価値系列化を従来の絵づくりに陥るものとして避け、個々のタッチをあくまで等価な世界の構成単位として置けるかぎり置き続けたのです。
運動としてとらえる事物の本質<充実>
セザンヌがタッチによってとらえたかったのは山の形ではなく、山の存在を満たし存在たらしめている何ものかでした。それを仮に<充実>と呼ぶとすると、彼が「感覚」する<充実>は山ばかりか自然のすべての存在を存在たらしめている根源的な要素でした。
彼は<充実>が山をはじめとするそれぞれの対象を成立させ、「生きられる世界」を具体化しているのだと考えたのです。対象に偏在する<充実>を、画面上に等価なタッチの重なりとして変換を試みたものが彼のいう「プランの魂」です。タッチによって即対象の形態を狙うのでなく、等価なタッチの重なりによる運動性が極まり、「プランの魂」が現前すればおのずと対象の確固とした形態が浮かびあがるはずでした。
細い色面のタッチによる微細に震えるような運動性を持続させながら、彼が待ち望んだのは、かつての古典絵画にみるような揺るぎない確固たる形態の登場でした。存在の根源である<充実>が「プランの魂」として現前する極みにまで絵画空間をつきつめることが彼の求める「感覚の実現」でした。しかしその表現概念の現象学的な転換からは、「ふたたびクラッシックに還らねばならぬ」とする彼の意図に反して強固な形態は生まれて来ず、そこには微細に震動する事物の輪郭や形態が集積されるばかりでした。「林檎がうごくか。」とモデルを叱る彼の苛立ちの原因の一端はそこにありました。
カメロン夫人の写真とセザンヌの肖像画
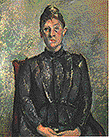
セザンヌ夫人像
1885-90
Paul Sezanne,
(1839-1906)
「セザンヌ夫人の肖像」1890 にみられる、彼のその矛盾をはらんだ対象への焦点の当て方は、映像のブレやボケを排除せずむしろそこに表現性を見い出したカメロン夫人の写真を思い起こさせます。彼女の写真は扮装をこらした対象を客体として鮮明にとらえることでなく、彼女が対象の在在の本質と感得する、人間という存在の移ろいやすくはかない美しさを写し出すことでした。
カメロン夫人のすぐれた写真をみると、説話的な扮装や設定を超えて、彼女が存在の本質として写真の粒子にとらえた、つかの間の美が強く浮かびあがってきます。

ある婦人の頭部像 1867
Julia Margaret Cameron
(1815-79)
カメロン夫人の求めるつかの間の美は、写真という機械にしかとらえられない微小時間の映像を追うことからではなくて、あくまで人間のとらえた対象のつかの間の姿を機械をとおして映像に置き換えることから生まれるものでした。彼女にとって写真は客体的世界の瞬時を追う道具ではなくて、彼女のとらえるつかの間という人間的な時間のうちに生起する世界を映像に定着するための道具でした。
瞬時をとらえる写真の特性から比喩的に言えば、シャッタースピードの遅い彼女の写真表現は、彼女の求めるつかの間にまで微小時間の映像が積み重ねられた像としてあることになります。
彼女にとっては言わばその集積された映像の厚みこそが必要だったので、そのために映像に現れてしまう、通常は写真家の不手際とされるブレやボケは問題ではありませんでした。
セザンヌの絵画はカメロン夫人の写真表現にみる、つかの間というロマン的な要素への還元ではなく、存在を満たしている根源的な<充実>そのものが追及されるのですが、両者に共通しているのは、客観的世界の対象を自己の世界観に見合う時間に引き寄せようとする執拗な態度です。
カメロン夫人は必然的に生じる映像のブレやボケのために技量が十分でない写真家とみなされることに悩まされねばなりませんでした。
一方、セザンヌの人物像はタッチによる画面上の運動の持続が優先されるために、肢体は硬直し表情が乏しく巧みな画家の人物描写と呼ぶには程遠い様相を呈することになります。
「リンゴが動くか!」とモデルを叱るセザンヌにとっては、静物も人物も彼の感得する存在の<充実>に満たされている限り同等の存在でした。「人間の生きている徴し」とは、その根底を<充実>に満たされていることからくる表面的な一現象でしかありませんでした。
「同時代の肖像画の達人達、例えば、マネやドガやルノワールに描かれた人間と比べると、セザンヌに描かれた人間達は、殆ど異様に感じる程、顔から表情を失い、姿態から運動を失っている。…」と小林氏が「近代絵画」で指摘するように肖像画の重要な要素であったはずの人物の表情、ポーズの優雅さはセザンヌの人物からは一切排除されています。
小林氏は生の徴しを失ったセザンヌの人物について、「どの肖像を見ても、一種物悲しい感情が漂っているが、そう呼んでいいものかどうかは解らない。私の感情は、私がこれを物悲しいと名付ける前に、もっと名付難い感情に既に確かに捕らえられて了っているようだ。」と述べています。
色面の運動性のうちに存在の<充実>が立ちあらわれるのをめざす彼の肖像画は、あたかも瞬時の映像を多重にかさねるかのように、タッチが置き続けられています。セザンヌの画面を満たしているのは「人間の生きている徴し」が消失してしまうのも構わず置き続けられたタッチです。
それは見る者の感情に訴える画面とは少し趣きを異にしています。小林氏が「名付け難い感情」に捕らわれざるを得ないのはそのためです。
存在の<充実>を感覚しようとするセザンヌの世界観は、「生きている徴し」を再現するレベルを超えて彼の表現性を押し上げています。
映像化からの離脱
セザンヌの現象学的な世界観は、モネが光学理論を援用したと同様の欠陥をもたらしました。彼がタッチの運動性を強めれば強めるほど、彼の絵画は対象の再現性から遠のき、対象の形態はその運動性のなかに解消して行こうとします。
セザンヌのタッチは対象をズルズルとその世界観にひきつけることになり、そのままでは印象派の技法と同様に、対象はその概念のなかに溶解していこうとします。
それは世界を一方向に還元しようとする現象学的な世界観の欠陥だといえます。
「再びクラッシックに還らねばならぬ..。」と主張するセザンヌは、対象の再現性を離脱しようとするタッチを対象の明確な構成要素、「円錐、球、円柱」に向わせました。セザンヌによって、絵画は強固な形態を自ら創り出そうとするあらたな方向性を与えられました。絵画は彼の営為によって再現性から離脱する方向に造形的な地平のひろがりをかいま見せました。
しかし「クラッシックに還る」として絵画の古典的枠組にこだわるセザンヌの営為は、あくまで絵画の再現性の内部での指向でなければなりませんでした。彼は、再現性と表現性が両手を組み合せたようにがっちりと結ばれた堅固な絵画の構造を求めていました。
「世間とは恐ろしいものだ。」と言うセザンヌの言葉通り、「世間」の映像化の動きに背を向けたはずの彼の営為も否応なくその「世間」のうちにあり、その成果は時代の時空のネットワークのなかに組み込まれ、その脈絡のなかでみられることは避け得ませんでした。
セザンヌが嫌悪したのは、「世間」の通俗的な価値観やそのなかから一歩も出ようとしない人々でしたが、心底脅威を感じたのは、いかなる個的な営為も呑みこみ、ネットワーク化して個人の意図せぬ機能のもとに位置づけてしまう、時代の時空の働き方ではなかったでしょうか。
そこにはいかに異なった位相の事象でも具体物である限りは映像として均質なレベルに対象化してしまう写真の力が少なからず加担しています。
写真は世界をどこまでも差異化しようとする、言わば上向きの動きを持つとともに具体的事象に下降し広く現象を網羅し、映像としてどこまでも世界を等質化する、言わば世界の広い裾野をすべて覆いつくそうとするかのように働きます。その意味では写真は科学の片腕であり、セザンヌの嫌悪した「世間」の価値観を強化し敷衍する強力な要素にもなっていました。
