
Cindy Sherman 1954-
- 1954
- ニュージャージー州グレン・リッジに生まれる。
- 1976 22歳
- バッファローにあるニューヨーク州立大卒業。
- 1977 23歳
- 芸術振興基金より奨学金を支給されニューヨークに住む。
1970年代末より「アンタイトルド・フィルム・スティル」
シリーズ始める。 - 1996
- 東京現代美術で「シンディ・シャーマン」展
Untitled Film Still #21 1978

「Untitled Film Still #21」, 1978
C・シャーマンは、映画のスチール写真の手法で写真を撮ります。若い女性は待ち受ける運命におののくかのように上方に不安げな視線を投げかけています。
この意味ありげなシーンはまるでヒッチコックの映画の導入部分を思わせます。 被写体の女性はシャーマン自身ですが、 はでなメーキャップといかにもお仕着せの服装は、彼女がすでにある物語のなかの存在であることをを示しています。
背景のビルや女性の服装からすると、写真の時代設定はニューヨークに高層ビルが建ち並び始めた今世紀の始め頃のようです。
田舎から上京したばかりの 若いヒロイン。 彼女は目的の場所が見あたらず、街の規模の大きさと喧噪に当惑し立ち尽くしているのでしょうか・・・。
それとも、事態は全く逆で、彼女はこの街を去ろうとしているところなのかも知れません。 ビルから出てきた彼女は、後にしたオフィスのあたりを嫌悪の情をもって振り返る・・・。それとも・・・。
写真の情景は私たちに読解をせまるばかりで、ストーリーの全体は作者の胸のうちに秘められていて決して明かされません。
記号のシステムのなかの写真
現代の都市文化にある私たちは、他の時代とは比べものにならない大量の映像イメージに囲まれて生活しています。 <記号のシステム>の側にあって映像イメージを作り出す仕事の広がりはテレビ、映画、商業写真、雑誌、広告、ビデオ制作、インターネットのホーム・ページ制作などに及んでいます。これらの映像イメージ制作を、今、仮に<映像デザイン>と呼びます。
<映像デザイン>の領域は、個人の幻想とは逆立する<システム>の側で映像イメージを作り出す仕事です。<映像デザイン>は、私達の願望をすくい上げて映像化し、それらを<システム>の側に反転させ企業の意図に重ね合わせイメージ記号とします。
私たちがスナップ写真を撮るとき、被写体の人物にポーズをつけてみたり、自身が写る場合も、にっこり微笑んでピース・サインをしてみたり、あるいはすましこんでみたりというふうに何らかの演出をし、最も好ましい「事実」をつくり出そうとします。(その演出の仕方は、今や<映像デザイン>の影響が大です。)私たちのスナップ写真の演出は、たわいのないものがせいぜいですが、<システム>の映像イメージの「演出」の度合いは私たちのスナップ写真の場合をはるかに超え、「事実」を反転させた虚構のイメージが制作されます。
例えば、商品の広告に使われる若い女性のアップの映像は、虚構の設定のなかでの笑顔であって、その商品が同じように魅力的であるという意味に重ねられるために作られます。そこでは若い女性はあくまで健康的に、多くの場合、明るく微笑んでいなければなりません。家族団らんの映像に登場する人物は幸福な、また時には不幸な家庭の一員を演じます。
登場人物は、たとえ実名で登場しても虚構の設定のなかの人物です。<記号のシステム>自体が私たち個人の日常とは逆立してたちあがる虚構の世界です。
その虚構のドラマの成立を支えているのは、映像は事実をそのまま映すものだとする私たちの映像に対する素朴な 位置づけです。それらは強固な固定観念となって<システム>が繰り出す大量のイメージ映像の虚構を支えています。<システム>の側、<映像デザイン>の領域から見れば、虚構の映像イメージを欲しているのは大衆であって、彼らはイメージ記号の虚構に酔いしれたいのだ、ということになります。大量の映像のイメージ記号に慣らされた大衆である私たちは、個と<システム>の反転を当然のことのように黙殺し、記号に当てがわれた虚構の意味を受け入れています。
<システム>の記号の世界では、現実のニュース映像さえも虚構のイメージ記号の一つです。

A・ウォーホル
「Satuerday Disaster」1964
208×152cm
Rose Art Museum.
事実を映すはずのニュース映像は、ただ現実を撮ったというだけでは十分ではなく、事件をより事件らしく見せる、<システム>のイメージ記号として最もふさわしい映像が選ばれます。
かつてウォーホルは、虚構の記号であるニュース映像を私たちが現実の像として受け取る事実を驚きをもって取りあげ作品化しています。
C・シャーマンの写真は、<映像デザイン>の手法を真似てつくられています。彼女の写真のシーンは、まるで広告のイメージ映像のように綿密に計画されつくり出されています。その映像は個の側で作られたイメージ記号であっても<システム>の側への転倒をあらかじめ想定してつくられ提出されます。 ただし、個のイメージ記号に負わされた意味は、シャーマン自身のうちに秘められたままにされます。
リキテンシュタインの選んだ漫画

「Untitled #92」 1981部分
C・シャーマンのスチール写真はかつてリキテンシュタインが漫画の一こま選んだことを思い起こさせます。
映画のあるワン・シーンや漫画の一こまには、全体のストーリーは忘れ去っても何故か長く私たちの記憶に止まるものがあります。それは漫画の一コマや映画のワン・シーンが私たちの無意識を強烈に刺激する記号だからです。
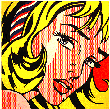
Roy Lichitenstein,
「ヘアリボンの少女
1965.
リキテンシュタインは前後の脈絡から切り離された漫画のワン・シーンを設定し、渦中にある女性に焦点を当てた作品を展開しました。彼は現代の都市の記号の一つである漫画のもつ強烈な指示性を取り上げ、芸術の記号としたのです。渦中にある女性のとりあげ方は両者に共通しています。シャーマンも同じ理由からスチール写真を選びます。
学生時代は絵画を専攻し、対象をそっくりに写すことは得意だったと語るシャーマンは、絵画を捨て写真を選んだ理由について、簡潔に次のように述べています。
「写真で撮れるものを何時間もかけてコピーする必要がない。その時間を、私は コンセプトに費やせる」 シンディ・シャーマン展図録, 東京現代美術館 1996.
女性アーティストの進出
都市の記号のシステムが完備強化された八〇年代、システム化された記号の領域を自らの個の領域とみなし、新たな表現を展開したのは女性アーティストたちでした。J.コススは次のように語っています。
「八〇年代のアート・シーンは女性アーティストの席巻に尽きるかもしれません。 本当に歴史をつくったのはジュリアン・シュナベール、サンドロ・キア、フランチェスコ・クレメンテ、アンゼム・キーファ、あるいはゲオルグ・バゼリッツのなか の誰でもなく。ホルツァーやクルーガー、それにシンディー・シャーマンとかサラ・チャールズワースだったのです」
意味の形成/歴史の形成 インタヴュー上田高広 美術手帳,1994 12.
コススが八〇年代のアートをつくったと指摘する女性作家たちの姿勢と右にあげられた新表現主義の男性作家のそれは好対照をえがいています。
新表現主義の作家たちは、<記号のシステム>がさらなる効率化をめざして進む方向に反対し、あえて逆行するコースをたどります。彼らは強化完備された<記号のシステム>に個の表現が回収されてしまう状況に対して、表現が記号化する以前にまでさかのぼり、表現の初源のエネルギーを取り出そうとしています。新表現主義の男性作家たちの営みは、退行のメカニズムによって時代の無意識をさかのぼり失われた表現性を引き出そうとする試みだといえます。
一方、女性作家たちは、<記号のシステム>が完備した現在の状況を受け入れ、記号がつくり出される領域をそのまま自分たちの表現を展開する場所とします。女性作家たちは、<記号のシステム>を、言わば彼女たちの<自然>の環境として受け入れるのです。女性作家の一人のC・シャーマンは、「私はメディアに起こっているすべてのことがらを認識している」と、<記号のシステム>について自分の住む界隈を知り尽くした住人のように語っています。
八〇年代の、一群の女性作家たちと新表現主義の男性作家たち、両者の行き方の違いは、ちょうど五〇年代の抽象表現主義の作家たちの表現が内面に向かう営みとしてあり、それを批判した次世代の作家たちの表現が、直接都市の事物や記号に向かったことの違いを思い起こさせます。しかし、この男女作家の動向の違いは、はたして男女の性差に還元されるものなのでしょうか?
記号化される女性の存在
シンディ・シャーマンは彼女のアート芸術表現に至った経緯について、自らが女性としてあることが重要なファクターだとして次のように述べています。
「もし、私がこの時代とこの場所に生まれていなければ、こうした表現をおこなうことはなかったでしょう。そして私がもし男なら、このような方法で、作品を生み出すことはなかったでしょう。」
東京現代美術館,1996,シンディ・シャーマン展で発行したカード。
彼女が身を置いた「この時代とこの場所」である現代都市は、都市の<記号のシステム>によって統御されています。そのなかで、彼女が女性であることはどのような意味持つのでしょうか?
現代都市はメディアから繰り出される「女」の記号にあふれています。性の要素のみを異様に拡大させた「女」の記号のあでやかさは、現実の女性から大きくかけ離れた虚像でしかありません。

Willem de kooning
1904- 「女1」1950ー52
かつて、デ・クーニングは巷にあふれる「女」の記号に自らの憎悪を向け自身の「女」の制作に取り組みました。彼が憎悪を向けたのは、彼をこれみよがしに挑発する記号の「女」と彼を含む実在の人間との落差です。
デ・クーニングは、都市の記号の裏に隠されてしまった現実の人間の存在を憎悪をもって探りました。
シャーマンは、学業を終えニューヨークに移り住んだ時、街がなんとも恐く、しばらく外出できなかったと語っています。記号と現実が錯綜する現代都市では、人々は記号化され、女性は自身がそのまま「女」の記号とみなされ得る存在です。
現実の女性であるシャーマンが、不意にデ・クーニングの表現する憎悪を浴びることも十分起こり得ます。彼女は、自身が「女」の記号を負わされ、見知らぬ他者から愛憎の目標とされ得る存在であることに恐怖しました。
「女」という記号は一体どのように彼女に負わされているのか?
また彼女自身の存在は「女」の記号の広がりにどう対応しているのか?
彼女は、自身を恐怖に陥れる「女」の記号の調査に乗り出します。
ヒロインの記号

Untitled C1975
C・シャーマンが最初に調べた「女」の記号は「少女」です。
彼女がかつて「少女」とみなされたことは何を意味するのか?
「女」のエロスから遠い無邪気な「少女」もまたひとつの記号にすぎない。
そうすると、夢に満ちた「少女」の時代も「少女」の記号の範囲に身を置いていたというだけに過ぎないことになる。
彼女は「少女」のメーキャップで再び自身をその記号に置き、「少女」の記号を調べます。
次に、彼女の調査は性(エロス)の記号としての「女」に移ります。そこでの彼女の設定は「女=ヒロイン」です。今や、シャーマンは自らの世界の大女優です。鏡の前で自身の容姿にみとれる「ヒロイン」、ベッドの上に下着姿で横たわり物思いにふける「ヒロイン」、飾り窓風の窓辺に腰掛け外を見る「ヒロイン」など、彼女は「ヒロイン」の記号のさまざまなシチュエーションを演じてみます。



左から , Untitled Film Still #35 1979, Untitled Film Still#6 1977, Untitled Film Still #15 1978.
自らが女優を演じるシャーマンの「女」の記号の調査は、彼女を「女」から自由にはしませんでした。
女性はなぜ、「女」の記号のなかにあることを要求される存在なのか?
彼女が自ら「女」の記号を演じることで調べるのは、「女」の記号と自身との落差です。しかし、演じられる「女」の記号は次第に彼女に密着し始め、彼女を「女」に近づけてしまいます。
そこで、彼女は古典絵画の記号の体系に入り込み、成熟した「女」から老齢の「女」、さらに「女」に対する「男」の記号をも演じ、自身に密着してくる「女」の記号から遠ざかろうとします。

Untitled #122, 1983.
しかし、彼女が「男」や「老女」を演じることで「女」から遠ざかろうとするとき、逆説的に浮上してくるのが彼女が女性であるという事実です。観客は女性である彼女がいつ彼女自身をあらわにするのかと、彼女の「女」の記号を調べる営みに潜むエロスに興味をよせ始めます。
シャーマンが自身をあらわにするとき、彼女はついに本来の「女」の記号としてあるのではないか?と。かつて大女優のモンローは、自分自身と記号化された「女」モンローのギャップに苦しみましたが、個人の世界の大女優を演じるシャーマンにも同じ事態が生じました。
彼女が制作したブランドファッション・メーカーのための写真では、高級服に身を包んだ女性は硬直した姿勢で拳を握りしめ「女」の記号と見られることを全身で拒絶しています。
マリソルの女

Escobar Marisol
「寄りかかる女たち」1963
硬直したシャーマンの女性の映像は、マリソルの人形とも彫刻ともつかない女性像を思い起こさせます。
彼女が都市の視線を浴びて硬直する女性像を制作したのは、先のシャーマンの作品のちょうど二〇年前です。その肉体は木の柱と化し、もはや自分で立つ事もかなわず壁に寄りかかっています。自らの尊厳を保つかのように顔を上げ、前方を見すえようとするものの、その目は固く閉ざされています。
二人の頭部は半分が壁にとけ込んで失われています。 硬直したとはいえ、その胴体はまだ彼女たちの肉体の線を止め、暖かさを感じさせる木の柱です。 石膏で型取られた彼女たちの表情は、むしろおだやかで、自らの運命をあえて甘受するかのようにみえます。
プライドがそうさせるのか、彼女たちは微笑んでさえいるようです。
シャーマンをさかのぼること二〇年、マリソルの表現した女性の硬直は愛玩される人形の位置に滑り込んだ女性の行き場のない姿です。 しかし、彼女のとらえる当時の女性の硬直には、まだ現実と折り合い優雅さを保つだけの余裕が感じられます。
シーガルの人体

ジョージ・シーガル「赤い籐椅子の少女」 1973
マリソルは自身の顔を石膏に取って作品に使いましたが、シーガルは人体をそのまま石膏シートで型取ることで知られています。 彼の表現する女性もまた、ある瞬間から突然動きを封じられ、その場に静止を強いられています。彼の女性像は「女」の記号の宿る表面である皮膚をはぎ取られ、匿名化した肉体、事物と化した存在です。 そこにはもはや、怒りを秘めた硬直はなく、弛緩したまま動きを封じられた化石のような肉体があります。
シーガルがこの作品を制作したのは、マリソルの「女たち」からさらに一〇年の後の一九七三年です。ここには、マリソルの「女」が辛うじて保つ存在の尊厳がもはや失われています。
今や、生きてあることの尊厳すら記号でしかないのだろうか?
人は表面の記号が奪われてしまえば、もはや動くこともかなわぬ肉塊の残骸となってしまうのだろうか?
シーガルの芸術表現は、私たちにそんな疑問と不安を突きつけます。彼の女性像は、完備を進める現代の<記号のシステム>のもとにある私たちの存在がさらに危うい基盤の上にあることを暴き出しています。
デュシャンの制服
デュシャンは、私たちが「男」または「女」として、社会から記号化された存在であることを考えました。それは、シャーマンの硬直の表現から六〇年前、マリソルの「女たち」から四〇年前の一九二三年です。
彼の「大ガラス」は、私たちが「男」または「女」といういずれかの性の記号を背負うことによって、相互に疎外される存在であることを表現しています。私たちが他者を「男」または「女」としてみる時、互いに異質な欲望のメカニズムのなかに相手を置くことになり、本来の存在はかき消されてしまいます。
デュシャンの「大ガラス」は、「男」「女」の欲望のメカニズムを、永遠に隔てられ決して交わることのない異なる位相の運動体として表現しています。

デュシャンの「大ガラス」
1915-23の部分
「九つの雄の鋳型」
その解明は他の機会に譲るとして、ここでは、デュシャンが取りあげた男性の記号をみます。男性は先ず、職業を通して存在を記号化される存在です。「制服とお仕着せの墓場」あるいは「九つの雄の鋳型」と呼ばれる部分がそれです。
そこには、彼がチェスの駒からデザインのヒントを得たと思われる、胸甲騎兵、憲兵、召使い、デパートの配達人、カフェのドアボーイ、僧侶、墓堀人、駅長、警官と呼ばれる九つの制服が並んでいます。
デュシャンは、職業自体を社会が人間にお仕着せる記号と考えました。それらの制服はまるで拘束服のように表現されていて、人間が社会の要求する鋳型にはめ込まれ、本来の姿から疎外されることがあらわされています。
男性が職業の持つ社会的地位によって自身の存在が定められ傾向が大であるのに対して、女性の場合、その存在を規定するのは、養育者を介した社会によってあらかじめ押し着せられた「女」の記号です。その記号によって、彼女がどのような職業の記号を選ぶか以前に、「女」としていかにあるべきかが厳しく問われます。
男性にとっても同様の事情があるとは言え、女性にとっては「女」の記号、「性」による疎外がくぐらねばならない最も大きな関門であることは現代においても変わりがありません。
デュシャンは「大ガラス」で「お仕着せの制服の墓場」として「男」の記号を集めましたが、シャーマンはその六〇年後、スチール写真によって女性にお仕着せられる「女」の記号を次々に収集します。彼女の「女」の記号の収集は、デュシャンが「男」の記号の集合に「制服とお仕着せの墓場」と名づけたことと呼応するように、次第に記号の「墓場」の様相を呈してきます。
死の匂う世界
「女」の記号はどこまで女性にまとわりついてくるのか? シャーマンは、「女」の記号が破綻をむかえ、女性を解放する地平をめざします。その地は死の世界です。

Untitled #153, 1985.
記号の死は肉体の死とともに訪れるのだろうか?
それとも死んだ女はまだ「女」の記号をまとっているのだろうか? さらなる「女」の記号を期待する観客は、生を離れることによって「女」をふり切ろうとする彼女のおぞましい変身につきあわされるのです。
人は幼い時期に誰しも一度は次のような空想にふけるはずです。<もし自分が今、死んでしまったとしたら、人々はどんな反応を示すだろうか? 人は私の大切さにやっと気づき、深い悲しみを味わうに違いない。私が死んだ後、父や母、友人が私の亡骸に取りすがって嘆く姿を、私自身がそっとどこかで隠れて見ることができたら、それはどんなに甘美なことだろう・・・>
シャーマンが「女」の記号をふり切るために死の世界をイメージするのは、少女シャーマンへの退行です。そこには、少女シャーマンがふくらませた死に対する空想がひろがっています。
<死後、獣に変身をとげる「女」がいたとしたら、それでも彼女はまだ「女」だろうか? 美しい「女」だった彼女の変身を目の当たりにする男どもはどれほど驚くことだろう・・・>
「世間は美しいものに、あまりにも気持ちが向きすぎています。だから私は通常グロテスクとか醜いとか言われるものを、もっと魅惑的で美しく見ることに興味を持つようになったのです。」
シンディ・シャーマン展図録 1996 朝日新聞社
「世間が見たがる美しいもの」とは、人々を欲情させる「女」の記号のエロスです。「女」の記号のエロスは、「女」の記号の調査を繰り広げるシャーマン自身にまとわりつきます。
「私の写真は、私についてのものではない。」「私はヌードになるつもりもない」と彼女が断らねばならなくなった時、シャーマンの自身を被写体とする「女」の記号の調査は、エロスにからめ取られその限界を迎えます。彼女は「女」のエロスから逃れ、再び「少女」に退行します。
人体模型の登場

Untitled #316, 1995.
シャーマンは自身が記号を演じることを止め、人形や人体模型を使うことを始めます。壊れた人形は愛玩される存在に甘んじることに疲れはてた女性の存在を象徴するかのようです。
<女性は「女」の記号を押し着せられてきた、その内面は今や醜くこわれた人形そのもののように疲弊している。 そんな醜くこわれた人形をあなたは変わらず愛玩できるのか?> かつての愛くるしさを醜い硬直に変容させた人形の表情は、そんな鋭い問いとなって私たちに迫ります。

Untitled #255, 1992.
医療器材の人体模型は、「女」の記号の持つエロスを零度にした単なる肉体の形態の記号です。シャーマンはエロスが零度に設定された肉体の形態の記号を使い、あからさまなポーズの写真を制作します。彼女は、エロスが零度のはずの「女」の記号が、人々に引き起こす反応を調べます。
「・・・いわゆる「セックス」を見せることに興味はありません・・・それよりも、性的な意味あいを含んだイメージを用いて、性的なものよりもっと大きな何かを表現することに興味があります。」
シンディ・シャーマン展図録 1996 朝日新聞社.
「性的なものよりもっと大きな何か」と彼女が言うのは、人間が性の記号「女」(「男」)によって疎外された存在であること、それに関わるエロスの働きを明らかにすることに他なりません。
<このおぞましい記号から解放される地平に到達できれば、私たちは互いに本来の人間の姿を見るはずだ。 そこに至るには、るいるいと横たわる記号の死骸を踏み越えて行かねばならない。> シャーマンの「女」の記号の調査は、時代の無意識を次第に下降し、死の匂いの立ちこめた荒涼とした地点に至ります。 そこが時代の精神の固着する場なのだろうか?
少女シンディは自身が味わった「女」であることの恐怖の代償に、「死」の記号をふりまき報復するのです。
