
Jasper Johns 1930-
- 1930
- ジョージア州、オーガスタに生まれる。
- 1949 19歳
- 2年間軍隊に入る。仙台に6カ月駐屯する。
- 1952 22歳
- ニューヨーク、ハンター・カレッジに入るが2日で退学する。
- 1954 24歳
- ラウシェンバーグと知り合い、ウインドーディスプレイで生活費を稼ぐ。
- 1958 28歳
- レオ・カステリ画廊で個展。
- 1959 29歳
- デュシャンを知る。
- 1973 43歳
- クロスハッチングを用いた制作始める。
photo:Jasper Johns Contemporary Great masters 講談社
*「旗のデザインを使ったお陰で別のレベルで仕事ができた」
“Using the design of the flag took care of a great deal for me because I didn’t have to design it…….
So I went on to similar things like the targets… things the mind already knows. That gave me room to work on other levels.” Jasper Johns
「旗」1954
ジョーンズは、都市の事物には必ず記号としての意味がこめられていることに注目しました。 そこで彼は大胆にも、アメリカ現代都市のなかで最上位に位置する国旗をモチーフに選びました。国旗は誰が見ても一目でそれと分かる記号です。

「旗」1954~55 107.3×153.8cm
The Museum of Modern Art, New York
国旗の記号としての強度は、国家という共同社会の価値観の強度と結びついています。 彼は個人の芸術表現によって社会の価値観の強度に挑むかのように、カンバスに写し取った旗のデザインにびっしりと絵の具や蜜蝋を塗りこめます。 彼にとっては前世代に当たる抽象表現主義の表現手法は、国旗を塗りこめるために使われ、都市の最上位の記号とその強度を競わされています。
それは、ジョーンズによって仕組まれた愉快で真剣なミスマッチでした。 彼は芸術を扱う手つきで、いかにも真剣に記号を扱い、都市の記号にあまりに従順な私たちの日常の<見る>行為を批判し笑いとばしたのです。 笑いとばしたと言うのは、私たちが彼の記号を芸術として扱う手つきを、同じく記号に従順な<見る>のレベルから<見る>にちがいなく、その真剣な手つきだけがつなぐミスマッチを芸術として<見>てしまうことも、確実だと予想できたからです。

大笑いジョーンズ
Inside the art world」
Barbaralee Diamonstein,
1993,
Rizzoli International Publications
「固有性の欠如と全面性のおかげで、ジョーンズ はこのクールなイメージの外側に感情的な負荷を自由につけ加えることができた」*
批評家、リチャード・フランシスの右の意見は、ジョーンズの表現に目を奪われた典型的な<見方>を示しています。その意見は、<ジョーンズは記号をモチーフにしたので、表現主義的な表現を自由にできた>と言うに過ぎません。
*「ジャスパー・ジョーンズ」東野芳明 美術出版社, 1979
それではまるでジョーンズが表現主義的な表現の発露をもとめて「旗」のデザインを選んだかのようです。この批評家のように、芸術の歴史的経緯を連続するものととらえると、現代美術の表現の意図は全く<見え>なくなります。 表現の表層を滑っていくこの<見方>こそは、まさにジョーンズの芸術表現が批判する都市の記号に慣らされた<見方>そのものなのです。 もし、彼が批評家として意図して都市の記号の側についた<見方>を取ったとすれば、その<見方>はさらに批判されるべきなのです。
ジョーンズは「旗」の制作について、「旗をいかに自己表現から遠ざけるという作業の課程である」*と述べています。しかしジョーンズの本当の意図は、その言とは違っています。 旗はもともと自己表現から遠いのです。彼の本当の意図は、絵画という自己表現(それはもはや無効になった抽象表現主義の絵画でした)に、自己表現から最も遠い現代都市の記号を飲み込ませ、記号から遠ざかった新たな位相に、いかに表現としての<絵画>を成立させるかにあったのです。 ジョーンズは、事物が負わされた記号によって事物本来のあり方を隠されている状況、即ち、事物の<記号による疎外>をあくまで当の絵画と記号を使って批判し、表現しようとしました。
彼は記号への批判を含んだ新たな<絵画>の形式をめざしました。
* 世紀の旗手の旅 辻井 喬 現代美術 第一三巻「ジャスパージョーンズ」 講談社 1993
あらわになった事物の地平
一九五〇年代の中頃、ジョーンズもラウシェンバーグと同じく、抽象表現主義が取った無意識の迂回路を通らず、直接都市の現実に目を向けた表現を始めます。 その頃すでに、絵画はすでにイメージを失い、ポロックによってその終着点に至っています。 ジョーンズ、ラウシェンバーグらが直面したのは、マス・メディアがイメージを占有し、絵画が事物としての相を完全にあらわにされた地平です。
ポロックがイメージを描くことを捨て、絵画の限界を超えてさらに表現性を強めたのは、すでに彼が事物の強度によって問われる地平に立っていたからでした。

作品に砂を混ぜるポロックJackson Pollock
The Museum of modern Art N.Y.
彼は絵具の代わりに塗料を使い、さらに画面に砂やガラス片を混ぜるなど、事物としての画面の強度をいかに上げるかに腐心し彼の表現が現実の事物の強度に打ち負かされてしまうことに抵抗しています。
すべての事物の機能が洗い直され、さらなる効率と機能が追求される現代都市では、伝統的な絵画の素材であった絵の具とキャンバスは、工業製品の耐久性や発色のすぐれた塗料や強度の均質な金属板、プラスチックなどと比較され、たちまちその貧弱さを露呈してしまいます。

「四つの顔のある標的」1955
ポロックの抵抗にもかかわらず、彼の芸術表現は都市のさらなる効率と機能を求める時間の流れに呑み込まれていきました。
「私が何をしても、人工的で嘘っぱちにみえるんだ….」というジョーンズは、事物の機能と効率を追求する時代の大きな流れのなかで、芸術の幻想がイメージを奪われ完全に無力化されてしまった地点に立っています。そこではかつての芸術の方法は、全く用をなさなくなっています。 ジョーンズは独学の人と言われていますが、かつての芸術の方法をどう展開しても「嘘っぱちに見えてしまう」という認識に至った以上、孤立して新たな視点と方法を探る以外に道はなかったのです。
事物の記号性によって疎外された<見る>行為
ジョーンズは現代都市のなかでの<見る>行為を取り上げました。彼は事物の記号性に歪められた私たちの認識に時代の<疎外>を見たのです。
都市の時間の流れを迅速化するのは事物の記号性です。日常の私たちの<見る>行為はそのは迅速な流れのなかにあります。信号を前にして、信号の色彩自体についてじっくり考える人はまれです。私たちに求められるのは、赤青黄色に振り当てられた意味を受け入れ、示された色によって素早く行動をとることです。信号に限らず、私たちの日常の<見る>行為は都市の求める知覚・判断・行動の一連のプロセスの一部です。
都市の空間では、見る行為は事物そのものを見るのでなく、事物に負わされた記号を素早く読みとることです。都市の迅速な時間の流れは、人々の思考と行動をパターン化しさらなる効率を求めます。
私たちの行動を指示する街の記号の例

歩行者用信号

ホームで整列乗車を指示する記号

駅の路線案内表示
ここで脈々と生きているのは都市のシステムの方で、人間は思考と行動をシステムに制御された機械のような存在ではないか? ジョーンズは、個として都市の記号の時間の流れのなかで立ち止まり、記号の裏側に封じこめられているはずの事物の生の姿を明らかにすることで、私たちの機械化された認識・判断・行動の姿を浮き彫りにしようとします。
ポロックの落胆
私たちの日常の<見る>行為は、事物の記号に順応した<見る>に限定されています。都市の事物は、そのまま記号の体系をかたち作っています。都市はその体系を介して、私たちに迅速な認識・判断・行動を強いるのです。芸術も一つの記号の体系として都市の記号体系のなかにあります。芸術に割りふられた機能は、人生の希望や悲哀を意味する読解可能な記号として都市を装飾し、都市の価値を高めることです。
ジョーンズから一世代前になるポロックは、自らの表現があらかじめ意味の定まった記号として読解され位置づけられることを拒否し、自らの表現を都市の記号の最上位に位置づけました。何故なら、彼は自らの表現を表現性が極限にまで高められた、精神そのものが事物化された究極の記号、精神の記号だと考えていたからです。しかし、都市は無情にも新参の芸術の一記号として、彼の表現を都市の記号の体系のなかに位置づけかえします。ポロックの憤慨と落胆はその位置づけの落差にありました。一九四三年にポロックが制作したグッゲンハイム邸の壁画は「高尚な壁紙」と批評され、彼を激怒させ、また落胆させました。
ジョーンズには、人々の絶対的な評価を求めるポロックはあまりにも無邪気に映りました。多くの人々は都市の時間に順応し、彼らの<見る>行為を事物の記号の面に限っています。ジョーンズには、彼らがすぐさま世界を深く認識し、画家の行為を理解する地平に立つとは考えにくいことでした。画家のなすべきは、むしろ、人々の認識と画家が事物の本質に踏み込んだ認識のギャップこそを表現の対象にすえ、人々の認識にゆさぶりをかけることでした。
ジョーンズの表現
ジョーンズの考えでは、私たちの日常の認識を支配する都市の記号システムの最上位にあるのは、ポロックの絵画ではなく(彼の期待に反して)、国家の記号である国旗でした。彼はそれを取り上げて作品にします。
「アメリカの国旗のデザインを使うことで私はずいぶん多くの無駄をしないですんだ。なぜなら、私は旗をデザインする必要がなかったからだ。私は同じようなもの、標的などを描きつづけた。つまり心が前から知っているものである。そのおかげで、私は別のレベルで制作することができた」
ジョーンズが「無駄をしないですんだ」と言うのは、ポロックの表現が芸術の新種の記号とみなされたのに対し、彼はその範に陥らずに現代都市の記号のあり方自体を問うことをめざせたことを指しています。
私たちの日常の<見る>行為では、私たちは星条旗を目にすればすぐさまそれを星条旗と認識し、しかるべき行動へと移っていきます。ジョーンズは国旗と言う記号のスムーズな働きに介入し、私たちにその認識の仕方自体に目をやることを促します。彼は、都市の記号化によってシステムとなってしまった<見る>ことを、もう一度私たちの側に引き戻し、共通概念の側に落ちていってしまう意味の形成過程を再び私たちの側へ引き寄せようというのです。それが彼のめざした新たな芸術表現でした。
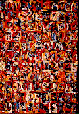
Small Numbers in Color 1959, Encaustic on Wood. 25.9×18.3cm.
ジョーンズは、国旗の次に、私たちの最も身近にあり、考える行為のツールとなっている記号を対象にしました。都市の最上部にある記号を取り上げた彼は、今度は一転して都市の下部、私たち自身に目を移し、私たちの思考の基底にある記号を取り上げるのです。
しかし、彼の方法を厳密に見れば、彼が取り上げるのは、数字や文字そのものではなく、数字や文字のデザインされた形です。それは国旗についても同様であり、その後の彼のモティーフの展開についても同じことが言えます。そこに彼の作品が現代の記号に対するより明らかな批判の表現に至らず、形についての行為、即ち現代の美の表現として変質し評価されてしまう余地がありました。
二つのエール缶

塗られたブロンズ 1960, Ludwig Collection Kunstmuseum Basel
次のジョーンズの取り上げた記号は大量生産品の上につけられたマークです。
ここでも彼のミス・マッチの戦略は同じです。彼はかつての<芸術>を扱うおもむろな手つきでこの記号を扱います。
どこにでも売っているビールの缶を二個、彼はわざわざブロンズで作ります。手作りを強調するためか、二つの缶の大きさは微妙に異なっています。缶の表面には、いかにも苦心した手つきで、つまり、手で描かれたことを充分強調して、マークが描き込まれるのです。観客はまたもや彼の戦略に陥り、このミス.マッチを<芸術>として、ためつすがめつ<見る>のです。その背後には、ジョーンズの高笑いが響いています。
グリーン・ボックスのメモ
「二つの似たもの(二つの色彩二枚のレース二つの形など)をそれと認める可能性を失うこと。一つのものからもう一つに似たものに記憶の痕跡を移行させるに足りる視覚の記憶の不可能性に達すること」
東野芳明氏は、ビール缶はジョーンズがデュシャンのグリーン・ボックスにある上のメモにヒントを得てこのビール缶を制作したと指摘しています。メモは難解ですが、<見た目がそっくりなら同じものだという常識、その常識をくつがえす表現を考えてみよ>と言う意味に取れます。ジョーンズはそれを事物の記号化の問題として考えました。
私たちは、日常では、同じマークのビールはどれも同じものと見なしています。都市のなかで記号化された事物に囲まれて生活する私たちの感性は、記号が同一であれば同一物と見なすことに慣らされています。 そのことは、都市の側から見れば、私たちは個別の差異を消去された員数の一人に過ぎないという現実と対をなしています。私たちの記号への順応は、人間をも外側のラベルで<見る>習性を養い、自身の像をますます薄っぺらなものにしてゆきます。
ジョーンズとデュシャン
六〇年代に入ると、ジョーンズは先人デュシャンの研究に打ち込んだと言われています。デュシャンには通称「大ガラス」と呼ばれる、アメリカ現代美術の先駆にして集大成とも言える作品があります。 その作品は、彼が近代芸術の終焉に立ち合いながら徹底して考察してきた事物と認識の問題を表現しさらにそれを組み合わせて出来ています。 後に展開するアメリカ現代美術のほとんどの概念を網羅していたのです。制作時のメモとミニチュアの作品群を複製し収めたのがグリーン・ボックスです。ジョーンズはデュシャンの考察態度、特に<見る>ことに対する考察を批判的に受け継ごうとします。

「独身者によって裸にされた花嫁、さえも」
1912-23
ジョーンズの表現は事物の記号化によって疎外された私たちの<見る>行為を批判しその回復をめざしたものでした。 ここで彼の取り上げた<見る>ことが私たちに果していた役割りをかんがえてみます。 かつて私たち人類は、<見る>ことを<考える>ことと連動させ、生産、文化、思想をかたち作るための基本ツールとしていました。 私たちの先人は、<考える>ことと<見る>ことを連動させ、事物のさまざまな局面をとらえ、事物と私たちの存在を照らし出す情報を引き出していました。
ところが、二〇世紀のはじめ、マルセル・デュシャンは、<見る>に偏った近代芸術を、あまりに「網膜的」だと批判し、<考える>ことの重要さを説かねばなりませんでした。
デュシャンの発言は、近代芸術が<見る>ことと<考える>ことの連動した運動を表現として保存し得なかったことを指摘し批判したものです。 この批判に対してジョーンズは、「絵画にあっては観念が伝えられるのは目に見えるかたちを通じてであり、それをさけるどんな道も私は知らないし、デュシャンにしてもできるとは思えない。」と反論しています。
両者の主張はかみ合っていません。デュシャンは作家の<考える>ことが鑑賞者をも巻きこんだ表現行為の総体から立ち現れることを想定しています。それに対し、ジョーンズは、<考える>こと自体を直接あわす絵画形式にこだわり続けています。
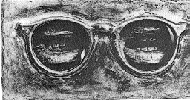
「批評家は見る」1965
ジョーンズが自らの<考え>(精神の営為)をあらわすものを絵画だとすることは、抽象表現主義の精神イコール絵画の図式を受け継いだことを意味しています。 彼はポロックの精神即、事物の表現という、近代芸術の到達点、終結点を引継ぎ、現実の事物の地平へ乗り出すなかで、なおも<絵画>を展開しようと試みます。
サルトルの実存
私たちが何を見、どう考えるかは本来私たちの恣意に委ねられているはずのものです。 サルトルは見ることを私たちの存在のあり方と自由、即ち実存に関わる問題だとしました。 ところが、都市は私たちのまわりの事物を記号化することで、私たちの知覚と思考を誘導し、私たちの自由を遠いものにしています。 彼は、私たちが「ものを知覚するときには、つねに一つの背景のうえに一つの形態が形成される」*と知覚における図と地のゲシュタルト的関係を指摘しています。ところが都市の記号はつねに事物の上に自らの形態を浮かび上がらせ、事物の他の要素を固定的に背景に退かせてしまいます。 日常での私たちの知覚は、常に自らを浮かび上がらせている事物の記号の上を滑っていくのです。 ジョーンズの<記号による疎外>の追求は、サルトルの言う実存の追求、自由をめざす営為とも重なっています。*「存在と無」J・P・サルトル、人文書院
都市の無意識を求めたジョーンズ
六〇年代には、ポップ・アートの表現が一斉に花開きます。その呼び水となったのが、ジョーンズの大量生産された商品の記号を取り上げた作品「エール缶」でした。ジョーンズを表現に駆り立てたのは、記号としてのエール缶が私たちの知覚、認識に起こす落差でした。 彼はそれを事物の記号と芸術の記号のミスマッチという構図で批判的に表現したのです。エール缶がミスマッチの威力を発揮するのは、私たちが、絵画、芸術を精神と同等のものとして至上の位置におき、かたや商品をその対極の事物のなかでも最下層にあると考える限りにおいてです。
ところが、ポップ・アーティストたちは、今や至上の位置を占めるのは私たちの精神ではなく、商品の方だと主張して、商品の記号を即、絵画として直結してしまいます。 ジョーンズには、ウォーホルやリキテンシュタインららのポップ・アートは精神の優位を放棄した、通俗に堕する表現と映ったはずです。 彼らは商品の記号が氾濫する現代都市の状況をそのまま受け入れながらその批判を含んだ芸術表現を展開するのです。 ポップ・アートの興隆はジョーンズの表現を成立させていた事物の記号と<芸術>の記号の落差を埋めてしまいます。 抽象表現主義以降の芸術表現として一世を風靡したジョーンズの表現は、自らが導いた後続のポップ・アートの興隆によってその命脈を絶たれるのです。彼の高笑いが響くのもここまででした。
以後、ジョーンズは、都市の記号の体系からすべり落ちた都市の事物に目を向けはじめます。彼にとって、絵画はあくまで個的な位相に止まり、社会的な概念(記号)と自らの概念のあり方との落差を<見る>行為を通して検証するものです。
ジョーンズは、街でふと目に止まった壁の模様 、すれ違った車に描かれていた縞模様など意味のない模様を素材にし、執拗に<絵画>とすることを試みます。

「Scent」1973-4, Encaustic and oil on canvas.182.9×320.7cm
「クロスハッチング」、「敷石」をモチーフとする彼の制作は無意味な事物に鬱々と拘泥しているようにみえます。 彼がこだわり続けるのは、絵画と精神を直結し至上の位置にすえることです。 彼は都市の記号からはずれ偶然のなかに漂う事物に表現の可能性を探ります。
*モティーフとなった敷石と八ッチング
この頃のジョーンズは偶然目にとまった事物をモティーフにすることによって都市の記号に縛られない表現の可能性を探る。
そのひとつが、彼がハーレムをタクシーで通ったとき見かけた壁の敷石模様。彼はそれに執着し、デヴィッド・ホクニーに写真を撮ってきてくれと頼むが見つからず、彼自身も探しに行くが見つからなかった。
もうひとつは、週末ハンプトンへ向かう車から、対向車に描かれた交差模様。これを見たジョーンズは、即座にそれを絵画に使おうと決めたという。
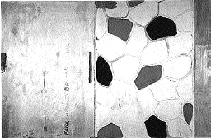
「Wall Piece」1968
ジョーンズは都市の無意識に漂う事物にあるしこりを見つけ、それが彼のなかで意味をかたち作る過程をさぐろうとします。
その表現は<記号による疎外>の表現ではありましたが、彼が批判しそこから出発したはずの抽象表現主義の内面の追究に再び向うことでもありました。
そこでは、かつて記号の落差を際立たせた彼の抽象表現主義風のタッチは彼の無意識をかき立てた事物へのこだわりを示すだけのものに陥っています。
再び<見る>ことの意味を求めるジョーンズは、自らの精神の内面を現代都市の底辺を漂うに重ね、孤独な面持ちで事物の偶然のなかをさまようのです。
